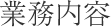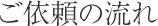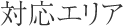就労継続支援B型の開業方法を行政書士が解説/青森県・弘前市

就労継続支援B型の開業方法を解説|法人設立、人員配置、設備基準などを詳しく紹介
就労継続支援B型とは、障害や難病を持っている方で、年齢や体力などの事情から企業などで雇用契約を結んで働くことが困難な方に対して、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練や支援を行う福祉サービスです。
就労継続支援事業には「A型」と「B型」の2種類がありますが、「B型」では、利用者と事業所との間に雇用契約は結ばれず、利用者は自分の体調や特性に合わせて無理のないペースで働くことができます。
近年では、障害者雇用の促進と共に、障害福祉サービス事業のひとつである「就労継続支援B型」の開業に関心を持つ方が増えています。しかし、B型事業の開業には、法人格の取得、人員配置基準、設備要件など、満たすべき条件が多く、準備には十分な時間と手間がかかります。
本記事では、就労継続支援B型の基本的な仕組みから、開業までに必要な準備や手続き、運営に必要な基準やポイントについて、行政書士の視点から詳しく解説します。
就労継続支援B型の対象者と支援内容
就労継続支援B型は、一般企業などへの就労が困難な障害者に対し、生産活動などの機会を提供し、知識・能力の向上を支援する福祉サービスです。対象者は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病等の理由で、雇用契約による就労が難しい方が中心です。
サービス内容としては、軽作業や物品の製造・販売、清掃、農作業など、利用者の状態に応じた業務を提供しながら、生活支援や社会的スキルの向上も図ります。
また、就労継続支援B型では、利用者との間に雇用契約を結ばないため、働く日数や時間について柔軟な対応が可能であり、利用者の体調や能力に応じた個別支援計画のもとでサービスが提供されます。
開業には法人格が必要
就労継続支援B型を開業するには、まず法人格が必要です。個人事業主では参入できません。法人の形態としては、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などがあり、いずれも開業は可能です。
ただし、社会福祉法人については、新たに設立するのが難しく、現実的には他の法人形態を選ぶことが多いです。合同会社や一般社団法人は設立の手続きが比較的簡易であることから、多くの方に選ばれています。
法人の設立後は、就労継続支援B型の指定を受けるために、法人の定款に「障害福祉サービス事業を行う」旨の記載が必要になります。これを見落とすと、後から修正が必要になるため、法人設立時には十分に注意しましょう。
人員配置基準を満たすことが必要
就労継続支援B型の事業所を開業するには、以下の人員を配置することが義務づけられています。
管理者
事業所の運営を統括する責任者です。常勤である必要はありませんが、法人の代表者が兼務するケースが多いです。
サービス管理責任者(サビ管)
利用者一人ひとりに対して個別支援計画を作成し、支援の内容や提供状況の管理を行う専門職です。原則として常勤が求められます。サビ管として勤務するには、相談支援や介護、福祉等の業務に一定期間従事し、かつ、所定の研修を修了している必要があります。
生活支援員・職業指導員
利用者に対して、日常生活や作業訓練に関する支援を行う職員です。生活支援員は、利用者の生活全般の支援を行い、職業指導員は作業に必要な技術指導などを担います。
これらの職員は、常勤換算で合計2.5人以上の配置が必要です。また、利用者の人数に応じて追加配置も求められます。たとえば、利用者が10人未満であれば2人以上、10人〜20人未満であれば3人以上、という具合に、職員の数は利用者数に応じて変動します。
設備基準もクリアする必要がある
事業所を開設するには、一定の設備要件を満たすことが必要です。主な設備要件は以下のとおりです。
- ・事務室
- ・相談室(プライバシーが保てる個室)
- ・活動・作業室(十分な広さと安全性)
- ・休憩室
- ・トイレ・洗面所(バリアフリー対応が望ましい)
建物の構造や内装、広さなどについては、各自治体の条例や要綱により若干異なる場合があるため、事前に管轄の自治体に確認しておくことが重要です。
また、建物の用途が「福祉施設」として使用可能であるかも、用途地域の制限や建築基準法の関係で確認する必要があります。既存の建物を借りる場合も、契約前に設備要件を満たしているか慎重にチェックしましょう。
指定申請の手続きと流れ
就労継続支援B型を開業するためには、「障害福祉サービス事業者」としての指定を受ける必要があります。指定は、事業所の所在地を管轄する都道府県または指定都市、中核市が行います。
指定申請から事業開始までの大まかな流れは以下のとおりです。
- 1.法人の設立・定款作成
- 2.人員の確保
- 3.物件の選定・設備の整備
- 4.指定申請書類の準備・提出
- 5.実地指導(自治体による現地確認)
- 6.指定通知書の交付
- 7.事業開始
申請から指定までには、1〜2か月程度かかる場合があり、また、申請書類の内容によっては補正(修正)を求められることもあります。余裕を持ってスケジュールを組み、早めに準備を進めることが大切です。
開業後の運営と収益モデル
就労継続支援B型は、障害福祉サービスであるため、主な収入源は「介護給付費(報酬)」と「生産活動収入(工賃収入)」の2つです。
介護給付費は、国や自治体から支払われる報酬であり、提供したサービスの内容や量に応じて算定されます。報酬体系は複雑で、基本報酬のほか、加算要件を満たすことで加算報酬が得られます。例としては、個別支援計画の作成加算や、送迎加算などがあります。
一方、生産活動収入は、利用者が行う作業によって得られる収益です。これは事業所にとって重要な自主財源であり、同時に利用者への工賃支払いの原資ともなります。
近年では、パンやお菓子の製造販売、農作物の生産・直売、清掃業務の受託、アート作品の制作販売など、多様な事業モデルが展開されています。作業内容の選定とマーケティングの工夫により、安定した収益を確保することが可能です。
まとめ:就労継続支援B型の開業は専門家のサポートが安心
就労継続支援B型は、障害のある方が社会とつながり、自分らしく働くことを支える大切な福祉サービスです。事業の社会的意義は大きく、地域社会への貢献度も高い分野といえます。
一方で、開業にあたっては法人設立から人員基準の確認、物件の選定、設備の整備、指定申請まで、多くの準備が必要です。また、自治体とのやり取りや各種書類の作成には専門的な知識が求められることも少なくありません。
スムーズな開業と運営のためには、行政書士など障害福祉サービスに詳しい専門家のサポートを受けることをおすすめします。申請書類の作成や自治体との協議対応などを代行・支援することで、手続きの不備や時間のロスを防ぐことができます。
これから就労継続支援B型の開業をお考えの方は、まずは専門家への相談から始めてみてはいかがでしょうか。
※香取行政書士事務所のサポートエリア
・青森県/弘前市・青森市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円
関連記事
おススメ記事
-

経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-

行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-

産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-

スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-

車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8